 |
|
TOP |
|
北陸工専労組 |
|
組合とは |
|
組合作り |
|
組合Q&A |
|
労働法とは |
|
労働委員会 |
|
相談掲示板 |
|
作成者サイト |
|
又市議員サイト |
|
メール |
|
リンク集 |
| 労働法規Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 労働法規とは | ||||||||||||||||||||||||||||
| 労働法規は、民法や刑法といった統一した法令が存在するわけではなく、労働基準法、労働組合法、職業安定法、労働者派遣法などの多数の法令が存在しています。 この中でも労働条件に関する最低基準を規定する労働基準法、労働組合に関して規定している労働組合法はたいへん重要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 労使関係と労働法規 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的には労使関係は対等な関係でなければならないはずです。 しかし実際には労使関係は使用者側が人事権を持っている事に由来してたいへん強大な権限を有していて、労働者側はなかなか対等な関係を結ぶことはできないのが実情です。 しかし使用者側の権限を無制限に認めていると労働条件の一方的な切り下げ、一方的な解雇などが横行して労働者の生活が守れません。これは一見すると使用者側が有利なようですが、結局は労働者の購買力が低下して企業の売り上げが減少し、自分のクビを絞めることにもつながります。 それで国家としても国家の生産力と経済活動を高めるために労働者の生活を守るための労働法規を用意しているわけです。労使関係は、基本的には契約から成り立ちます。ですから一度締結した契約は、一方的に破棄したり変更したりはできないのが民法の精神です。しかし労使関係においては、ややもすればそんなことがまかり通っているというわけです。そのため労働基準法で労働契約に関して最低限の規定を用意して、それを下回るような労働契約は無効とするわけです。これを強行規定といって個別の労働契約に優先する効力があるのです。 労働基準法は、労働関係に関しては民法にも優先します。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 就業規則と労働協約とは | ||||||||||||||||||||||||||||
| 労働基準法は強行規定ですので、使用者側が定める就業規則に対しても優先します。 ただし、就業規則は、ある程度使用者側が一方的に設定できます。もちろん労働基準法の規定を下回るような規則を設定はできませんが、例えば退職金などの規程は労働基準法でも絶対条件とはなっていないので、退職金に関する規定を盛り込まなくてもいいわけです。これですと労働者はかないません。 このような労働条件を改善しようとしても、労働者個人の力だけでは使用者側には対抗できません。そのためには労働者が団結して労働組合を結成して使用者側に対して労働条件の改善を要求する必要があるわけです。 労働者の団結権と労働組合の活動を保護するために労働組合法が規定されています。実は、日本の労働組合法は労働組合に対して強い保護が加えられていて、使用者側は労働組合に対してほとんど手が出せなくなっています。労働組合を結成する目的は、一口で言うと労働条件を改善するためですが、具体的には労働協約を使用者側と締結することです。労働協約は労使間の取り決めですが、これは労働組合法で就業規則に優先する法的効力があります。もちろん就業規則自体を改善できればなお良いのですが、使用者側も就業規則はなかなか改善しようとしない事があります。 つまり労働協約は、最大3年間という有効期限があるのでそれを過ぎると90日の予告期間により破棄できるのに対して、就業規則は一度改正すると今度はなかなか改悪はできない意味があるからですね。 ということで労働組合としては使用者側と団体交渉を重ねることで労働条件を改善していくことが任務であると考えれば良いでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 使用者側の違法行為に対しての法的手段とは | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用者側が労働法規を遵守し、就業規則や労働協約を守っている場合は良いのですが、それを逸脱した違法行為を犯す場合があまりにも多いようです。労働基準法の規定は強行規定ですので、これを守らない場合は刑事罰があるということを労使共々よく理解していないことが多いようです。刑事罰が与えられると、罰金刑といえども前科一犯になってしまうわけです。また労働組合法には不当労働行為という違法行為が規定されています。これは、以前は強行規定であったのですが、現在の規定は原状回復主義になっています。つまり使用者を罰するよりも労働者を保護する事を主眼に置いているわけですが、実際には使用者側に対して自分が違法行為を犯したことを看板で宣伝する(ポストノーティスといいます)ことが命じられたりして、たいへんな恥をかかされるのです。労働者側が使用者側の違法行為に対して対処する手段は次のような方法が考えられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 裁判所での民事訴訟 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
例えば労働者が不当に解雇されたり、不当な労働条件の切り下げを行われたりした場合には、地方裁判所に対して民事訴訟を起こすことが考えられます。不当解雇の場合によく利用される方法は、地位保全の仮処分申請と呼ばれるものです。これは、従業員としての地位を仮に認めることを申し立てるもので、3〜4ヶ月で命令が出るのですが、この際に賃金の仮処分も申し立てておけば、勝訴した場合には使用者側は賃金を仮払いしなくてはならなくなります。
ただし、敗訴した側は高等裁判所に即時抗告することができます。
最近では、「みちのく銀行」事件と呼ばれる民事訴訟が最高裁で判決が出ていますが、これは55歳以上は賃金が半減するという不利な労働条件を突きつけられて多数組合がその提案を受け入れたのに対して少数組合が承知せず民事訴訟を起こしたものです。 最高裁では少数組合の主張を認めて高裁の判決を破棄差し戻ししています。あまりにもやりすぎの労働条件切り下げは多数組合が承諾したからといって合理性があるとは認められないという新判例が出たということで画期的な判例です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 都道府県労働委員会への不当労働行為救済申し立て | ||||||||||||||||||||||||||||
| 労働組合がある場合は、労働組合法第7条に規定されている不当労働行為があった場合に対して、都道府県労働委員会へ救済申し立てをすることができます。都道府県労働委員会は、各都道府県に設置されていて、公益委員、労働者委員、使用者委員が同数で委員会が構成されています。富山県都道府県労働委員会では、5人ずつの委員が任命されています。また労働厚生省の外局として中央労働委員会があり、都道府県労働委員会で審査された救済申し立てに対して不服がある場合に再審査を行います。不当労働行為はつぎのような場合に成立します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 労働基準監督署に訴える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用者が労働基準法に違反している場合には、労働基準監督署に訴えることができます。労働基準監督署は、司法警察員の資格もあるので、労働者側が使用者側を告訴することもできます。ただし、実際には告訴までには及ばず、行政指導という形で使用者側に警告を発する場合が多いようです。給与、残業手当の未払いがあった場合は、労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 労働局に個別労働関係紛争のあっせんを申し立てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 労働局は個別労働関係紛争に対してあっせんを行う制度があります。 これは使用者側が不当な行為を行っているが訴訟にするまででもない場合に個別の労働者が労働局にあっせんを申し立てるものです。 ただし、あっせん自体には法的拘束力がないので、これで解決しない場合は、もっと強い措置をとる必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5) 都道府県労働委員会に労働争議の調整を申し立てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県労働委員会に対して救済を申し立てるほどではないが、地労委に紛争に介入してもらい解決を目指す制度があります。 調整には、あっせん、調停、仲裁の3種類があり、後者ほど強い効力があります。しかし通常は、もっとも利用しやすいあっせんが行われています。 ただし、労働局へのあっせんとは違って個人で申し立てることができません。労働組合か争議団を結成しないと調整を申し立てることができないわけです。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
あっせん・調停・仲裁の特徴一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者の立場と法的措置の関係についての図解 | ||||||||||||||||||||||||||||
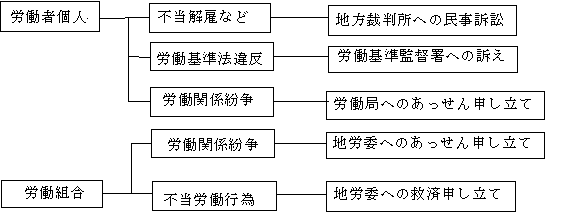 |
||||||||||||||||||||||||||||
| これからもわかるように都道府県労働委員会に申し立てする場合は、労働組合からでないとできないことがわかります。 原則として個人では地労委には申し立てできないわけです。 ただし、個別労働関係紛争のあっせん申立ては個人でも可能ですが、強制力はありません。 裁判所は誰でも申し立てすることができますが、訴訟費用や弁護士費用がかかります。 労働基準監督署への提訴は限定的ですし、労働局のあっせんは法的拘束力がありません。 労働組合があるとこれだけでも有利なのがわかります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
具体的な事案について
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ここでは実際の現場でよく見られるようなトラブルについてその法的解釈と解決方法について挙げてみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1)試用期間について | ||||||||||||||||||||||||||||
|
試用期間の間は自由に解雇できますか。また、何か法律的な規制があれば教えてください。
【回答】
試用期間は入社後、労働者を正社員として本採用するまでに、職業能力や企業適応性を見るために設けられた制度で、法的性格については、使用者の解約権が留保された労働契約と解されています。
試用期間中の解雇や本採用の拒否は、この解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されます。
しかし実際の判例では、試用期間中の解雇に関しては使用者側にかなり広い裁量権が許されているといえるので試用期間中には使用者側につけ込まれるようなことは避けた方が賢明です。
さらに試用期間中の解雇に関しては、解雇予告手当も支払われません。(労基法第21条4項)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2)労働契約 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】
労働契約を締結するにあたって法律で規制されていることを教えてください。
【回答】
労働契約締結にあたって、使用者には労働条件の明示が義務付けられています。
(労基法第15条1項)
期間の定めのある労働契約を締結する場合には、上限が決められています。(同法第14条)
労働契約に付随するものとして、損害賠償の予定、前借金相殺、強制貯金が禁止されています。(同法第16条、17条、18条)
また、労働組合法では、雇用の条件として労働者が組合に加入しないこと、労働組合を脱退することを義務付ける約定(黄犬契約)を禁止しています。(労働組合法7条1号)
労働契約には期間の定めのあるものとないものがあります。労働契約の期間は、現在は契約締結にあたって書面による明示が義務付けられています。 期限の定めのある労働契約を締結する場合、その期間は1年を超えることは許されません(労基法第14条)が、例外も定められています。 期間の定めのある場合、期間途中での解約はやむを得ない理由がない限り認められません(民法第626条)が、期間が満了すれば、その契約は自動的に終了することになります。 しかし期限のある労働契約であっても、契約期間が満了した時点で更新すると、次回の契約満了時点で使用者が契約を更新しない(いわゆる雇い止め)という場合は、合理的な理由がないと不当解雇とされる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
求人募集の際に示された労働条件を見て、応募して内定となりました。その内容は、昨年をベースにした見込みのものでした。入社手続時点で、業績向上が思わしくないとの理由で正式の労働条件だとして、内定で示されたものとは異なった低い条件のものが示されました。この低い条件のものに従わなければならないのでしょうか。 【回答】会社の明示した見込の労働条件の内容は、必ずしも守られない事があります。 採用前に明示された労働条件が採用時点で異なれば、労働者は労働契約を解除できます。 使用者は公共職業安定所への求人の申し込みによる労働者の募集においても労働条件の明示義務が課されています(職安法第5条の3)。 このため、使用者は求人募集のために明示する労働条件を示す求人票の記載時点で現行の初任給額または、それを上回る初任給見込額を記入し、入社日において、正式な賃金確定額を明示するような場合があります。 これにより、労働者は予想外のため入社にあたって使用者への信頼関係を著しく悪くするような問題が発生することにもなりかねません。法的に考えた場合、一般的には見込額は確定額でないため、請求権は発生しないと考えられます。 使用者側に十分な理由もなく入社日またはその直前まで労働者に告知しなかったような場合、または確定額が大幅に下回る場合には、応募者の期待に企業も誠実に対応すべきとして、労働契約上の違反として、損害賠償が認められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 子育てが終わったので、労働時間が自由となるパートタイムで働くことにしました。知人の紹介で面接に行き、その場で採用が決まりました。緊張しているときに労働条件の説明を口頭で言われたため、よくわかりませんでした。このまま確認をしないで働きにでていいものか迷っております。何か、はっきりとした労働条件を求めることはできないでしょうか。お教えください。 【回答】 使用者は賃金・労働時間などの労働条件をパートタイム労働者であっても明示する義務があります。主要な労働条件は、口頭で行うことは認められず、必ず書面によることが求められます。 労働条件の明示は文書であれば、問題はないわけですが、その示された内容にもれがあったりすることもありますので労働条件通知書で行うよう依頼してみてください。 パートタイマーは、平成5年に施行されたパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」と規定しています。これに該当する人はどのような呼称であっても、パートタイム労働法上の「短時間労働者」として取り扱われることになります。 またパートタイム労働者は、労働者保護法令である労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法等が適用され、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法についても一定の要件に該当すれば適用となります。 パートタイム労働者の採用には、労働条件の明示、労働契約の締結という所定の手続きが必要になります。 使用者は、パートタイム労働者として採用する者に対して、労働基準法に定められている賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。 文書による明示は賃金に関する事項だけでしたが、平成11年4月以降は、労働基準法の改正により次の4項目が追加されています。 1.労働契約期間 2.就業場所および従事業務 3.始業・終業時刻、所定外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務 4.退職 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3)賃金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 この数年、新聞などで、「年俸制」を導入した会社がしばしば紹介されていますが、私の勤務する会社でも、賃金制度を改めて年俸制を導入する動きがあります。そもそも年俸制とはどのような賃金制度なのでしょうか。また、年俸の額が決められた場合、時間外労働の割増賃金は別途払ってもらえるのでしょうか。」 【回答】 年俸制とは、賃金の額を年単位で決める制度ですが、典型的な年俸制では、労働者本人と上司等が話し合いにより、毎年の賃金額が変動しうる点に特色があります。 年俸制のもとでも、労働時間規制の適用除外がなされず、また、裁量労働や事業場外労働のみなし時間制が適用されない限り、時間外労働に対する割増賃金は別途支払う必要があります。 深夜勤務の場合は、いずれの場合も割増賃金を支払う必要があります。 最近の判例では、大阪府内の男性(24歳)が以前つとめていた測量会社に、未払い賃金(時間外労働分の割増賃金)の支払いなどを求めていた事件で、大阪地裁は「年俸制の採用で、直ちに時間外割増賃金を支払わなくてもいいことにはならない」として、年俸制を理由に割増賃金を支払わない会社に対し、時効分を除く割増賃金など計約120万円の支払いを命じました。 男性は、平成9年4月、同社の正社員になりました。 測量の仕事は不規則で、時間外勤務も多くなるなどを理由に年俸制で賃金の支給を受けました。 約3年後、男性は公共事業担当になって時間外労働が多くなり、割増賃金の支払いを求めましたが、会社は「賃金は年俸制で、残業代もこれに含まれている」として応じませんでした。 男性は、昨年1月に退社しました。 判決では「労働基準法は割増賃金を支払うことで、超過労働を制限している。同社は、基本給と割増賃金を一体で支給しているというが、同社の給与明細では、どの部分が基本給か明確でない。割増分が確認できない支払い方法は、同法に違反する」とされて原告側の主張を認めています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 私の勤務先には、特に賞与の支払を定めた規定はありませんが、10年ほど前に私が入社する以前から、毎年2回、年により変動はあるものの、夏は月給の2ヶ月分ほど、冬は月給の3ヶ月分ほどの支払いを受けてきました。社長は、今年の冬は業績が悪いので賞与は払えないかもしれないと言っているのですが、賞与とはいかなる場合に請求できるのでしょうか。 【回答】 賞与は、法律上当然に使用者が支払義務を負うものではありませんが、就業規則などにより支給基準が定められている場合や、確立した労使慣行により、これと同様の合意が成立していると認められる場合には、使用者は、労働契約上、賞与を支払う義務を負います。 この場合は、そうした労働協約や就業規則の定めはないので、以上の他に労働契約上の根拠があると言いうるかが問題となります。もっとも、この点については、すでに10年以上にわたり、年2回の賞与が支給されるという取り扱いが繰り返されてきたとのことですし、その額についても、一応の基準はあるとみてよさそうです。 そうすると、本件においては、特段の事情がない限り、賞与の支払いについては、すでに労使慣行が成立していると言って良いでしょう。 そこで問題は、こうした労使慣行がいかなる意味をもつかですが、一定の取り扱いが長期にわたり反復して行われ、しかもそれが当事者に規範として承認されるに至った場合には、黙示の合意が成立したものとして、あるいは民法92条の事実たる慣習として、労働契約の内容となります。 このように言える場合には、就業規則などの規定において賞与の支払義務が定められていなくとも、労働者は賞与の支払請求権をもつと言えるでしょう。 後は、労使の力関係の問題です。労働組合があり労働者側に力があれば、交渉により賞与を支払わせようとするでしょうが、それがない場合に個別に交渉しようとしても難しいでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 私はパートタイマーとして近所のスーパーマーケットで働いていますが、パートの賃金には、地域の最低賃金が影響を与えているという話を聞きました。最低賃金とはどのようなものなのでしょうか。 【回答】 最低賃金には、最低賃金審議会の調査審議にもとづく最低賃金(職権方式)と、労働協約にもとづく地域的最低賃金があり、前者が一般的です。 最低賃金(職権方式)には、都道府県ごとに決められた地域別最低賃金と新産業別最低賃金とがあり、日額と時間額で金額が示されています。 しかし現在は日額が廃止され、時間額だけが決められています。 富山県の最低賃金は、時間額644円です。 しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある下記の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。 1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方 2)試用期間中の方 3)認定職業訓練(事業主等の行う職業訓練の申請を受けて、都道府県知事が認定を行った訓練)を受けている方 4)所定労働時間が特に短い方、軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4)労働時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 労働時間についての法規制はどうなっていますか。 【回答】 労働時間の法規制は、現在では1日8時間、1週40時間が原則的な上限となっていますが、弾力的な労働時間制度も増えつつあります。 労基法上の労働時間の規制は実労働時間によるのが原則で、使用者は通常労働時間を把握する義務を負います。 さて、1週・1日の労働時間規制に関しては、労基法32条により、使用者は、労働者に、休憩時間を除いて、1週40時間を超えて労働させてはならず(1項)、かつ、1日8時間を超えて労働させてはならない(2項)とされています。 これに違反して労働者に労働させた使用者には、刑事罰による制裁がありますし(119条)、労働者とこうした規制に違反する合意をした場合でも、その合意は無効となり、無効となった部分は上記の基準のとおりに修正されます(13条)。 労基法33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働)や36条(いわゆる36協定)などにより、一定の要件のもとに時間外労働をさせることはできますが、その場合でも、使用者は割増賃金を支払わなければなりません(37条)。 36協定とは、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。」と規定されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 当社では来月従業員に休日出勤をさせる必要がありそうですが、他に暇な日もあるので、休日の振替で対処したいと考えています。 休日振替を行う場合は、割増手当を支払う必要はあるのでしょうか。 【回答】 労働基準法上の休日とは、労働契約上予め定められた、労働者が労働義務を負わない日をいいます。 休日振替は、就業規則上の規定や労働者の個別的合意に基づき、事前に振替休日を指定して行いますが、労基法上の週休制の原則に違反しないようにする必要があります。 労働基準法35条1項により、使用者は労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。労基法は、1日8時間・1週40時間を法定労働時間とし、週休2日制を想定していますが、週休2日制は要求せず、最低基準としては週1日の休日を要求するに留めています(また、同法35条2項は、変形休日制による例外を認めています)。 休日の振替とは、他の労働日(振替先)を休日(振替休日)とする一方、従来は休日であった日に労働者を労働させることをいいます。では、このような措置により、労基法36条に基づく協定の締結と割増賃金の支払をせずに、すなわち時間外労働として取り扱うことなしに労働させることができるでしょうか。 ここでは、まず、休日振替は労基法に違反しないかが問題となりますが、労基法35条により、休日を振り替えた後の状態が週休1日の原則(変形週休制をとる場合は4週あたり4日)に従うことが要求されます。 この要件をみたせば、次に述べる手続により振り替えた休日の労働は、休日労働とは評価されず、36協定の締結や割増賃金の支払は不要となります。 もっとも、休日振替の結果1週間の法定労働時間を超える場合には、36協定の締結と時間外割増賃金の支払が必要です。 次に、振替先の労働日が休日になるかという問題があります。この点については、振替先をあらかじめ示して振替を行う場合には、振り替えた休日に労働義務が発生する一方、振替先の労働日は、労働契約上あらかじめ労働義務がないものと定められた日として、休日になると評価できます(ただし、労基法の規制に違反する場合には、こうした振替の効果は生じません)。 さらに、使用者は労働者の個別的同意を得ずに休日振替を命じうるかという問題もありますが、就業規則において、業務上の必要性があることを振替の要件とするなど合理的な根拠があれば、使用者は個別的同意を得ずに休日振替を命じうると考えられます。 裁判例および行政解釈も、使用者が休日を他の労働日に振り替えることができる旨を定めた規定が存在し、振替先の労働日をあらかじめ特定すれば、使用者は労働者の個別的同意を得ずに休日振替を命じることができると解しています。 以上に対して、あらかじめ振替先を指定しないで休日に労働させ、後にこれに代わる休日(代休)を与える場合は、休日の変更はなされていないため、休日労働が行われるものと評価せざるをえません。 したがって、このような場合は36協定と休日割増賃金の支払が必要となりますので、注意が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 当社では、所定労働時間は午前9時から午後5時30分(正午から午後1時までは休憩)までですが、午後5時30分から午後6時までの残業に対して割増賃金の支払は必要でしょうか。 【回答】 労基法上の時間外労働や深夜労働に対しては通常の労働時間の賃金の2割5分以上、休日労働に対しては通常の労働日の賃金の3割5分以上の割増賃金の支払が必要です。 労基法の範囲内でなされた所定外労働に対しては、労基法上は割増賃金を払う必要はありませんが、特別の定めがない限り、就業規則などにより所定外割増賃金を支払うべき場合が多くなります。 使用者が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で命令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条1項)。 割増率は、時間外労働については2割5分、休日労働については3割5分と定められています。 以上の他、使用者が労働者に対し、午後10時から午前5時までの間に労働をさせた場合には、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。 (37条3項) 労基法33条や36条に従って適法な時間外・休日労働がなされた場合の他、違法な時間外・休日労働についても、使用者が割増賃金支払義務を免れないことはいうまでもありません。 また、労基法上の割増賃金については、労使で支払わないものとする合意をしても、そのような合意は労基法13条により無効となります。 時間外労働と深夜労働とが重複した場合、および休日労働と深夜労働が重複した場合には、割増率は合算され、それぞれ5割以上、6割以上となります(労基則20条1項・2項)。 しかし、休日に1日8時間を超える労働がなされても、割増率は3割5分以上でさしつかえありません 割増賃金は、「通常の労働時間の賃金」または「通常の労働日の賃金」に、割増率および時間外労働数または休日数等を掛けて算出します。通常の労働時間または通常の労働日の賃金とは、(1)時間により定められた賃金についてはその金額、(2)日により定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日により異なる場合は平均時間)で割った金額、(3)週により定められた賃金については、その金額を1週の所定労働時間数(週により異なる場合は平均時間)で割った金額、(4)月により定められた賃金については、その金額を1月の所定労働時間数(月により異なる場合は平均時間)で割った金額、(5)月、週以外の一定の定められた賃金については、(1)ないし(4)に準じて計算した金額、(6)出来高払制その他請負制によって計算された賃金については、その賃金算定期間における総労働時間数で除した金額、などをいいます(労基則19条)。 ただし、家族手当および通勤手当(労基法37条4項)のほか、別居手当、子女教育手当、一定の住宅手当(住宅に要する費用に応じて算定されるものに限られます。平成11.3.31基発170号)、臨時に支払われた賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(労基則21条)は、算定基礎から除外されます。除外賃金にあたるか否かは名称に関係なく実質的に判断されますが、除外賃金に含まれない賃金を割増賃金の算定基礎から除くことは許されません。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 解雇・退職 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 いきなり会社から口頭で解雇を申し渡されましたが、このようなことが許されるのですか。 【回答】 解雇については、労基法に一定の労働者に対する解雇禁止規定と手続き的な規制があるだけでなく、均等法、労組法などにも一定の規制があります。 法律上の解雇規制としては、労基法19条による解雇禁止規定の他、同法20条の解雇予告期間及び解雇予告手当に関する規定がありますし、同法3条の労働条件に関する均等待遇原則は解雇にもおよびます。 また均等法は8条において解雇の場合の男性との平等取り扱いを規定していますし、労組法7条は労働組合員であることや労働組合の正当な活動の故をもって解雇することを不当労働行為として禁じています。 さらに労基法104条2項は、労基法違反などについて労働基準監督署等へ申告したことを理由とする解雇を禁じています。 また、今回の労基法改正で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と明記されました。 家庭生活と職業生活との調和をはかる趣旨では、育児・介護休業法第10条及び第16条が、育児・介護休業の申し出または育児・介護休業したことを理由とする解雇を禁止していることにも注目する必要があるでしょう。 しかし労基法上も労組法上も解雇してはいけないとは書いてありません。 民法上の解釈からすれば、継続的契約を解除することは一定の手続きがあれば可能というのが当然の帰結になるので、解雇自由となってしまうわけですが、最高裁判例ではこの解釈を認めず、合理的な理由がない限り解雇無効という解釈がなされています。 これまでの裁判所の判例では、整理解雇4要件と呼ばれる整理解雇が正当化される条件が確定しています。 整理解雇とは、従業員の従業員の事情によるものでなく、使用者の事情によるものであるから、これまでの判決ではかなり厳しい次のような要件を要求しています。 (1)人員整理の必要性 企業が経営危機に陥り、企業の存続のためには人員整理が避けられない事情があること。 (2)人員整理の回避努力 配置転換、希望退職者の募集等余剰人員の吸収に努力、役員報酬の削減その他諸々の経費削減努力をしたが、なお人員整理が必要であること。 (3)人選の合理性 人選基準が合理性を有し、その適用も合理的、公平なものであること。 (4)手続の妥当性 人員整理の必要性、人選基準等につき労働者側の納得が得られるように努力していること。 これらの条件を満たせば、整理解雇できると言うわけですが、実際にはばらつきがあるので、全ての条件を満たすかどうかには言及せずに解雇を認めたケースもあります。 このような場合、まず会社側に書面で解雇の事実とその理由を求めて、それがない場合は解雇自体を認めないこと、もし解雇理由を含む回答が書面にてなされた場合は、それを持って直ちに弁護士または労働組合等に相談なさることをおすすめします。合同労組などに加入なさって組合側から交渉してもらうのも良い方法です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 わが社は従業員20人の零細企業なので、通常の退職金を払う余力がありません。退職金というのは、必ず払わなければならないのでしょうか。 【回答】 民間の企業については、法律上必ずしも退職金の支給義務はありませんが、退職金は職業生活引退後の重要な資金となりますので、できるだけ安定的に支給される必要があります。 そこで、制度上も判例上も、退職金が確実に支給されるよう様々な工夫がされています。 公務員の場合と異なり、日本では民間企業の従業員に対する法律上の退職金支給義務は使用者に課されていません。 したがって民間企業では、必ずしも退職金を支給する必要はなく、現実に雫細企業などでは退職金制度を有していない場合も少なくありません。 しかし、日本の雇用慣行の中では、退職金は引退後の生活設計の基盤となる重要な原資として重視されてきましたし、その額が月額給与はもちろんのこと、賞与等と比べても大変大きいのが通常であるという事情も手伝って、できるだけ退職金制度が普及し、かつ確実に支給されるような工夫が、法制度の上でも試みられています。 まず、労基法89条は、就業規則の記載事項として「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」をあげています(三の二)。 ここでいう退職手当とは、労使間において、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確になっており、その受給権が退職により在職中の労働全体に対する対償として具体化する債権であればよいとされており、支給形態が退職一時金であるか退職年金であるかは問いません。 また、使用者が、中小企業退職金共済制度や適格年金制度、調整年金制度等の社外積み立て型の退職金制度を利用している場合も、ここにいう退職手当の制度に該当しますので、就業規則規定を設けなければなりません。退職手当の決定、計算及び支払の方法とは、例えば、勤続年数や退職事由などの手当額を決定するための基準、あるいは手当額の算定方法や一時金と年金のどちらで支払うのかなどをいいます。 さらに、退職手当について不支給事由または減額事由を設ける場合には、退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するので、就業規則に記載する必要があるとされています(昭63・1・1基発第一号・婦発第一号)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 不況を理由に上司から退職届を出すよう強要され、やむなく提出しました。しかしこれは本意ではないので撤回したいと思います。法的に可能でしょうか。 【回答】 基本的には、退職勧奨に応じて退職届を提出したことで、退職の合意は成立したものと見なされます。しかし上司の退職勧奨に不法性があったと認められれば、裁判で争うことも可能です。 退職届の提出は、法的には、労働者から会社に対する労働契約解約の申し込みと解されます。この申し込みを会社が承諾することによって、労働契約解約の合意が成立することになります。したがって、会社から、本人の退職を承諾する旨の意思表示がなされる前であれば、退職届の撤回は可能です。 ただし、この場合は、会社の承諾の意思表示がどの時点で行われたかが問題です。退職辞令や退職承認通知書等の交付という明確な手続きがあれば明らかですが、退職届に対する退職承認の決定権のある者が「被上告人の退職願を受理したことをもって本件雇用契約の解約申込に対する上告人の即時承諾の意思表示がされたものというべく、これによって本件雇用契約の合意解約が成立したものと解するのがむしろ当然」(最三小判昭62.9.18 大隈鉄工所事件)という判断もあります。 次に、退職届の提出が本人の意思ではなく、上司から強要された場合にはその撤回が可能かという点を考えてみます。 まず、強要されたかどうかは別にして、会社から退職を勧告されて本人がそれに応じた場合は、会社からの解約申し込みを本人が承諾したことになり、その時点で合意解約は成立したものと考えられます。 そこで次の問題は、退職を強要されたという点をどう解するかです。この点に関しては次の判例があります。 「任意退職の勧告がかりに不法な企図ないし誤った認定に基づくものであるならば、不服な被勧告者は、これに応じなければよいのであり、一旦これに応じて退職願が提出された以上、その提出が承諾となり、雇用契約の合意解約が成立し得ることは当然であって、その合意解約が有効か無効かは、別に考察すべき問題であり、任意退職の勧告の不法性が、必然的に合意解約の無効を来すものではない」(神戸地龍野支判昭38.9.19 播磨造船事件) 他方、退職届の提出が本人の自由意思によらず真意に反した強制にもとづくものであるとして無効とされたケースもあります。 これは事業不振を理由とした退職勧奨ではなく、辞表を出さなければ懲戒解雇だと圧力をかけて退職届を提出させた事件ですが、このケースでは、退職届の提出は脅迫による意思表示であり、その後の本人の撤回申出により取り消されたことにより、合意退職は成立しないと判断しました(宮崎地判昭41.3.10 宮崎交通事件)。 このように、強制された退職届を後日撤回することは法的には可能ですが、裁判になった場合には、上司による退職勧奨に不法性があったかどうかが争点になるものと思われます。具体的に上司にいつどのような強要を受けたかについて記録を残しておく等の備えが必要と思われます。 しかし、何よりも大切なことは、退職を強要された場合、本意ではないのに退職届を提出してはならないということです。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 7)労働協約・就業規則 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 会社の中に労働組合を結成しました。今後の労使関係の基本ルールや労働時間制度、賃金の評価システムなどについて使用者側と概括的な妥結に達しましたので労働協約を締結しようと思います。 労働協約には特別な意義や機能があると聞きましたが、その概要を教えてください。 【回答】 労働協約は、労働組合と使用者(団体)との間でのみ締結することができる書面協定であり、契約としての一般的な機能の他、規範的効力(労組法16条)や一般的拘束力(同法17条、18条)などといった特別な効力が付与されています。労働協約の機能は、このような特別な効力を基盤として公正で安定的な労使関係を築くことに主眼が置かれています。 労働協約とは、労働組合と使用者とが取り交わすさまざまな協定、取り決めなどのうち、労組法14条の要件を満たしたものをいいます。これによれば、労働協約と認められるためには、書面に記すことと、締結両当事者の署名または記名押印が必要とされています。これらの要件を満たして労働協約と認められない場合には、後述する規範的効力や一般的拘束力などの、労働協約独特の効力を有しないことになります。 労働協約に期間の定めを付する場合は、上限は3年と規制されており、これをこえる期間の定めは、3年の期間を定めたものとみなされます(労組法15条)。また、期間を定めない場合には、継続的な契約関係を解約する場合の通例に従って、予告期間を設けた上で解約することになりますが、労働協約については、この予告の日数は90日とされています(同条)。 したがって解約当事者は、解約すべき日の遅くとも90日前に解約の意思表示をしておく必要があります。 さて、労働協約の最も主要な機能は、労働条件の基準を定めることですが、これについては労組法16条が、いわゆる規範的効力と称される特別な効力を労働協約に対して付与しています。 すなわち、「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」を定めた労働協約については、これに反する労働契約の定めはその部分については無効となり、無効となった部分は労働協約の基準がこれに代わることとされています。 しかも「労働契約に定めがない場合」も同様とされていますので、結局、労働協約の「労働者の待遇」に関する定めはそのまま労働契約上の合意と同じ意義を有するということになります。 これについての問題はいくつもありますが、一つは、労働協約が失効した場合、その後の労働契約はどうなるかで、一般には労働協約の「余後効」の存否という形で論点とされています。これはドイツの議論をそのまま日本に移し替えたものですが、新協約が締結されない間の労働条件をどうするか、といった実際上の問題にもなりえます。いまだ定説といえるものはありませんが、最高裁は、労働協約の内容を反映して規定された就業規則がある場合には、当該協約失効後はその就業規則によるべきであるという事例判断を提示しています(最一小判平成1・9・7 香港上海銀行事件 判時1383号164頁)。 また、具体的な労働協約の内容が、どれほど労働組合員にとって不利益であっても規範的効力が及ぶか、といった問題も、労働条件切り下げの手段として労働協約の規範的効力が利用されるような場合には重要な問題となりますが、これについては、最高裁は、当該規定の内容が、特定の個人またはグループをことさらに不利益に扱うことをあらかじめ目的として締結されたなど、「労働組合の目的を逸脱して」締結されたような場合以外は規範的効力に支障はないとしています(最一小判平成9・3・27 朝日火災海上保険(石堂)事件 労判713号27頁)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 最近、我々の労働組合以外に別組合が結成され、それが過半数を占める状況となりました。 そして会社側がその別組合と労働協約を締結し、それを元に我々の組合員だけが著しく不利になるように就業規則を改定しました。このような就業規則は有効なのでしょうか。 【回答】 この件は、一応法的な手続きについては適正になされているわけですから、これを覆すには多数派組合を切り崩して、多数派を握って、再度労働協約を締結するか、訴訟で就業規則が無効だと主張するしかないでしょう。 最近の判例では、「みちのく銀行事件」という最高裁判例があります。 みちのく銀行は、基本的には年功序列型賃金体系を採用していたが、高コストで収益力の弱い企業体質を改善し、経営効率を向上させるため専任職制度を創設(第一次変更)し、昭和61年5月1日からこれを実施した。 さらに、60歳定年制の関係から高年層への人件費の偏在化を改善するために専任職制度の改正(第二次変更)し、昭和63年4月1日からこれを実施した。 これらの就業規則の変更は、多数組合の同意は得たものの、少数組合の同意を得ないでなしたもので不利益変更にあたるとして無効を主張し、地位確認等の請求と仮執行の現状回復を申し立てた事件です。 第一審では、原告の主張が一部認められたものの、第二審では原告側が敗訴し、最高裁に上告していたものです。 最高裁は、不利益の大きさ、変更の相当性が認められないことなどを理由に、多数派の同意を考慮してもなお合理性は認められないとし、破棄差し戻ししました。 これまで最高裁において、就業規則の不利益変更につき合理性を認めないとの判断を示した判決は2件しかありませんでしたが、本判決は、原審を覆し、しかも正面から合理性判断を行った上でこれを認めなかった最高裁判決としては初めてのものとして注目されます。 つまり、この判決は多数派組合が同意し、労働協約を締結してそれに基づいて就業規則を改定した場合でも、少数派組合のみが著しく不利益を被る場合には合理性が認められず無効になることがあるということを示しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 8) 労使紛争の解決について | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 会社から労働契約期間が今月末で満了するとして、その日をもって退職することを通告されました。私はまだ年齢も若く、働き続けたいと思い会社と話し合いたいと希望しましたが、会社は拒否しています。当事者で話し合う状況ではないため、弁護士を交えての話し合いをすることにしました。弁護士費用もかかるため、何か良い方法がないかお教えください。 【回答】 労使紛争で困り弁護士依頼を考えたときは財団法人法律扶助協会が実施しています。 法律扶助を受けることをおすすめします。 弁護士への支払費用だけでなく、実績・評判を確認して依頼することです。 法律扶助制度は、国民の権利の平等な実現をはかるために、弁護士による援助及び裁判のための費用援助等をする制度です。この制度の実施団体は財団法人法律扶助協会です。 財団法人法律扶助協会は、法律上の扶助を要する者の権利を擁護し、もってその正義を確保することを目的としています。 財団法人法律扶助協会(本部:東京都千代田区霞ヶ関1−1−3弁護士会館14F電話03−3581−6941)の目的を達成するための事業は、 1. 資力の乏しい者に対する訴訟費用等の立替え 2. 弁護士の紹介 3. 弁護士による法律相談 4. 民事訴訟の保全処分に関する支払保証 5. 法律扶助に関する調査・研究 6. 法律に関する知識の普及、広報及び出版物の刊行 7. その他協会の目的達成に必要な事項、となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 9) 男女均等について | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 男女の賃金差別について特に禁止した規定がありますか。どのような差別が禁止されるのでしょうか。 【回答】 労基法第4条は、男女同一賃金原則を規定しており、女性であること自体を理由とする差別を禁止しています。違反した場合には刑罰規定があり、女性労働者は男性との差額賃金の請求、あるいは賃金差額相当分の損害賠償を請求することができます。 労働基準法第4条は「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない」と規定しています。国際的には、同一価値労働に関する男女同一報酬が国際条約で繰り返し確認されてきており、我が国もこれを定めたILO第100号条約を批准しています。 労基法第4条によって賃金差別が禁止されるのは、女性であること自体を理由とする場合です。行政解釈では、女性が一般的に勤続年数が短い、能率が低い、主たる生計維持者でないことなどを理由に、実際にそうであるかどうかを問わず一律に賃金の男女で異なる扱いをするのは賃金差別に該当するとし、職務、能率、技能、年齢等により現実に賃金に差異が生じても、差別にはあたらない(昭和25.11.22婦発31号)としています。 同条は差別的取扱いを禁止しているので、女性を男性より有利に取扱うことも禁止されます。 同条違反の具体例としては、男女別の賃金表の設定、女性の年齢給の頭打ち、住宅手当や家族手当の男性のみへの支給、男性は月給制であるのに女性は日給制などがあげられます。 判例では、家族手当の支給を世帯主とした場合で、家計の主たる担い手である収入の多い方とした場合には労基法第4条違反とならないとした事例(東京地判平元.1.26 日産自動車事件 労民集40巻1号1頁)、配偶者に所得税法上の扶養控除限度額を超える所得があるときには男子のみを世帯主と扱う場合は4条違反になるとした事例(仙台高判平4.1.10 岩手銀行事件 労民集43巻1号1頁)や、本人給を実年齢に即して上昇させるか、26歳で頭打ちにするかを、当初は「世帯主」か否か、新しくは「勤務地非限定か」否かを基準としているという制度が、ともに女性が一方的に不利になることを容認して制定されたものと推認され、女性であるということを理由とする賃金差別として認めた事例(東京地判平6.6.16 三陽物産事件 労判651号15頁)などがあります。 男女同一賃金原則違反については、刑罰規定があり(労基法第119条)、労働基準監督署による是正指導が行われます。また、これに違反するものは法的効果としては無効であり、就業規則や労働協約に差別的な賃金規定があれば無効となります。差別により損害を与えれば、賠償責任が生じることになります。差別を受けた女性(男性)労働者が差額賃金の請求をなしうるかについては、判例では過去の賃金差別の額が確定できる場合に差額請求を認めた事例(前掲 岩手銀行事件、山陽物産事件)や客観的な支給基準がなく使用者の意思表示による場合に不法行為による賃金差額相当分の損害賠償請求を認めた事例(東京地判平4.8.27 日ソ図書事件 労判611号10頁)があります。また、賃金差別が一見明白な場合は、使用者の側でその合理性を立証しない限り、性別による賃金差別と推定された事例(秋田地判昭和50.4.10 秋田相互銀行事件 労民集26巻2号388頁)があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【質問】 労働法では女性労働者はどのように保護されていますか。また、妊娠中の女性や出産後の女性について、配慮すべき点を教えてください。 【回答】 労基法では、坑内労働と母性機能保護に必要な危険有害業務の就業の禁止を除き、女性労働者に対する一般的保護規定は撤廃され、妊産婦のみに対する保護規定を定めています。 また、産前産後の保護、育児時間、生理日の休暇が定められています。 均等法で新しく妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する規定が義務化されました。 成9年に改正された労基法(平成11年施行)では、女性労働者に対する一般的保護規定は撤廃されました。これは次のような経緯によります。 労基法制定当時は、戦前の工場法の伝統を受け継ぎ、女性労働者を生理的・体力的に弱い面のある労働者と認識し、広範な保護を規定していました。しかし、女性労働者に対する伝統的「保護」の多くは固定観念に基づく、現在では合理性のない制限で、女性の雇用機会を狭め男女「平等」の妨げになるという認識が国際的にも定着し、主要先進国では一般的女性保護はほとんど廃止されてきました。我が国でも昭和60年の均等法制定と同時に、労基法の女性保護規定については、妊娠・出産にかかわる母性保護の機能を強化する一方で、それ以外の面における女性労働者の保護が縮小されました。そして、平成9年に改正された均等法(平成11年施行)で、女性労働者に対する平等が強化されるのに伴って、労基法も改正され、女性の時間外・休日労働の制限と深夜業の禁止が全廃されました。 時間外・休日および深夜業の規制が撤廃されたため、満18歳以上の労働者は、男女を問わず同じ条件で、時間外・休日労働および深夜労働を行うことができます。しかし、規制が撤廃された結果、女性労働者の家庭生活に重要な影響が生じるおそれがあるため、平成14年3月までの経過措置として、育児・介護を行う女性労働者に対し、厚生労働大臣が労基法第36条2項に基づき定める時間外労働の上限の基準において、本来の基準とは別の年150時間以内のより短い時間が定められています(労基法第133条)。詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。 他方、女性の深夜業に関しては、「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針(平成10.3.13労告21号)」が出され、防犯面での安全の確保、育児・介護等に関する事情聴取等の配慮、男女別の仮眠室・便所・休憩室の設置、健康診断等の措置の実施を事業主に求めています。また、育児・介護休業法の改正で、子を養育する労働者・家族介護を行う労働者は男女を問わず、深夜業の制限を使用者に請求することができるようになりました。 現在でも女性一般の就業が禁止されているのは坑内労働で、坑内では一部の業務について女性の就業が例外的に許容されているのみです(労基法第64条の2)。また、妊産婦(妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性)には危険有害業務に対する就業制限がありますが、重量物を取り扱う業務や有毒物のガスや粉塵を発散する場所での業務は、女性の妊娠・出産機能に有害であるとして女性労働者一般に関して禁止されています(労基法第64条の3第2項、女性則3条)。 女性労働者の中でも妊産婦については労基法上特別の保護規定が置かれています。妊産婦の妊娠・出産・哺育等に有害な業務への就業が禁止されており(労基法第64条の3)、その具体的範囲は命令で定められています(女性則2条)。坑内労働禁止の例外も妊婦および申出をなした産婦にはその適用が否定されます(労基法第64条の2)。労働時間についても妊産婦が請求した場合、変形労働時間制の不適用(労基法第66条1項)、時間外・休日労働の禁止(同条2項)、深夜業の禁止(同条3項)となります。また、妊娠中の女性が請求した場合には、使用者は他の軽易な業務に転換させることを義務付けられています(労基法第65条3項)。 また、均等法では、事業主に対し、妊娠中及び出産後の女性労働者に対して、母子保健法による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することや、そこでの指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じることを義務付けています(均等法第22条、23条)。 労基法では、女性労働者が出産する場合、産前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)、産後8週間の休業が認められています。産前休業は本人の請求が条件となっており、産後休業は強制ですが、そのうち最後の2週間については、本人が請求すれば、医師が差し支えないと認める業務に就業することが許されています(労基法第65条1項、2項)。産前産後休業中の賃金の支払いは義務付けられていませんが、健康保険から1日につき標準報酬日額の60%の出産手当金が支給されます。産前産後の休業期間中およびその後の30日間は、解雇が禁止されています(労基法第19条)。 また、労基法では1歳未満の子を育てる女性労働者が請求した場合、使用者は、法定の休憩時間のほか、1日2回、各30分以上の育児時間を与えなければならないとされています(労基法第67条)。 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合については、使用者はその者を生理日に就業させてはならないとされています(労基法第68条)。 なお、産前産後の休業や生理日の休暇については、判例では精皆勤手当の算定にあたり生理休暇取得日を欠勤扱いにすることは、当事者の取り決めに委ねられた問題であって、生理休暇の取得を著しく抑制しない限り違法でないとしています(最三小判昭和60.7.16 エヌ・ビー・シー工業事件 民集39巻5号1023頁)が、昇給・昇格の要件である出勤率の算定上、産前産後の休業、生理休暇取得日、育児時間を欠勤扱いとすることは、経済的不利益の大きさから労基法上の権利行使への抑止効果が強く、公序良俗に反し無効としています(最一小判平元.12.14 日本シェーリング事件 民集43巻12号1895頁)。 |