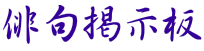 平成14年2月分会員作品 |
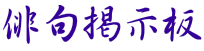 平成14年2月分会員作品 |
| 平成十四年二月 例会 照子選 |
| 白梅を追う紅梅に今朝の鳥 |
| 木枯しに押され小走るハイヒール |
| きらきらと闇の灯台春浅し |
| カーテンを引き残したる雪月夜 |
| この道に五十五年や鍬始め |
| 橋の上水仙根ずきて香をはなつ |
| 冬カモメ頭上をかすめたじろけり |
| 初場所や横綱またも休むらし |
| きさらぎの波が引きゆく砂利の音 |
| 大試験絵馬に祈りをかけてをり |
| 誰を待つ少しうつむく水仙花 |
| 腰痛や夫にわびつつ寝正月 |
| 冬の朝牛の匂いのみな元気 |
| 冬かもめ一羽一羽に光もつ |
| 風花や子規の碑まだらなり |
| 寒椿一際庭を円くする |
| 枯野道風が遊んでをりにけり |
| 待合室夫の身案ずる桃の花 |
| 初雪に浮かぶカモメの波枕 |
| 南国の風花土にとどかざる |
| 白梅と思えどかすかに紅ほのか |
| 厄落とす思いそれぞれ辻の豆 |
| 大寒の鉄骨を組む響きかな |
| 愛犬の死を告げて来る初便り |
| 寒の入り夕日眺めて露天風呂 |
| 木枯しの満月鈍くひかりけり |
| 山門に梅の花散る石畳 |
| 犬ふぐりひよこに名前付けている |
| 古里の川ゆったりと猫柳 |
| 娘と枕並べて旅の冬ぬくし |
| 福ばかり呼んで豆まく闇の中 |
| 春の雪落つる所を目で追ひぬ |
| 町二つ踏まえて輿り時雨虹 |
| 母と娘の待ち針あつめ針祭る |
| 作品 | 作者 | 寸評 |
| 左義長や焦がした餅を妻と分け | 二宮武夫 | *左義長はドンド焼きのこと。よくわかる句 |
| 大枯野の真ん中をバス突っ走る | 竹崎恵美 | *上五の「の」は不要 |
| つまずきし石を見ている寒さかな | 菊地芳子 | *なぜつまずいたのであろう。寒さの故か年齢の故か |
| あれも捨てこれも忘れて炬燵かな | 神童 | *やや言葉の遊び的な句ですが、「捨てたり」「忘れたり」する中で人生の生き方がある。 |
| 送り出す後ろ姿や大試験 | 三好文尾 | *初投句。気づかぬ母の姿が見える |
| 花売りの藁で束ねる梅の花 | 浅川道子 | *花も野菜も藁で束ねるのが一番よい。 |
| 寒経の一人の声の甲高き | 河野ミツエ | *一人だけの声が耳について寒さが身にしみる。 |
| 来月の大会に期待している。 | ||
| ※気になったこと |
| ・文語文と口語文の混用 |
| 例として失礼ですが 春だなあ木偶の三番曳が舞ひにけり 宮本ミユキ 「春だなあ(口語文)木偶の三番曳が舞ひにけり(文語文)混合です。」 「さんば」と読むより「さんばそう」として「春浅し木偶の(さんばそう)舞ひにけり」としては。 字余りは結構。 |
| ・古今の名句は平易な文字や言葉で作られています。 |
| 分かりやすい文字・言葉で俳句を作りましょう |