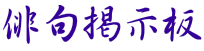 平成13年6月分会員作品 |
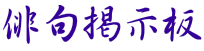 平成13年6月分会員作品 |
| 今月の内容 |
| 平成13年度第33回吉田町俳句大会 |
| 定例会 「傳選」 |
| 六月作品寸評 石帆 |
| 賞・選者 | 作 品 | 作 者 |
| 「教育長賞」 | 蛸うごく諸行無常のかたちして | 神童 |
| 「特選」 佐怒賀正美選 | かげろへる船かげろへる船を曳く | 稲垣千代子 |
| 池内けい子選 | 頭から目刺しを食ふて戦前派 | 宇都宮傳 |
| 井上論天選 | 頭から目刺しを食ふて戦前派 | 宇都宮傳 |
| 宇都宮丸台選 | ぶらんこを降りて地球を歩きだす | 神童 |
| 古墳掘る幾万年の風光る | 宮本ミユキ |
| 賞・選者 | 作 品 | 作 者 |
| 「特選」 大崎康代選 | 電波の日乳ふくむ子の眼天を駆く | 河野ミツエ |
| 井上論天選 | 母として役目まだあり梅漬ける | 西村さつき |
| 長谷ミツル選 | 犬が追い子が追ふ路地のしゃぼん玉 | 神童 |
| 作 品 |
| 文豪の残り香によふ薔薇の園 |
| 濃紫陽花歴史を語る顔の傷 |
| 夏場所や獣のごとき力士の眼 |
| 戸を開けて聞く真夜中のホトトギス |
| 百合開く母十七年の忌を修す |
| 耳遠くなるが気になる春の雷 |
| 鐘の音を包む須崎の若葉風 |
| 姉夫婦古布で作る夏の帯 |
| 花蜜柑護る生涯この里に |
| 夫退院とっておき笑顔更衣 |
| 卯波寄す音の迫力桂浜 |
| 親も子も遠足疲れバスの中 |
| 菖蒲湯でコミニケーション父と子が |
| 墓に出し百足なりせば逃しやる |
| 車椅子押して五月の南楽園 |
| 満潮に小魚きらきら夏来る |
| 名を呼ばれはにかむ子等に初夏の風 |
| 筍を目当てに薮へおづおづと |
| 熱き骨拾うや新緑の山迫る |
| とろとろと煎りし新茶の黒ずみし |
| 土手歩き川面を泳ぐぼらの稚魚 |
| 四万十へ園児が放つ稚鮎かな |
| 葉桜も一際深く影を敷き |
| 庭園の水のせせらぎバンガロー |
| さっそうと若者の行く若葉道 |
| 留守頼む夫に買い置く柏餅 |
| 夕日落つ植田の色を引き寄せて |
| 枝えだに絡みし藤の濃紫 |
| 試着室ウエスト気になる更衣 |
| 草笛を吹いて見たくて土手に来し |
| 作 品 | 作 者 | 寸 評 |
| 戸を開けて聞く真夜中のホトトギス | 三好 雪 | 当地では五月中旬頃夜空を鳴き乍ら渡るのをよく聞きます |
| 老鴬の遠く響くや峡の町 | 井上雅代 | 朝立ちの山まで津布理や揚の鴬がきこえます |
| 紫陽花や心に泌みる寺門訓 | 二宮武夫 | 寺門訓と季語が調和して「心に泌みる」が生きる |
| 卯波寄す音の迫力桂浜 | 西村さつき | 卯波と雖、土佐の桂浜の波の力強さは格別 |
| 渓谷の水の色こく夏来る | 山本真津子 | 水の色こくで「夏来る」に真実感が出た |
| 満潮に小魚きらきら夏来る | 宇都宮美直子 | これも「夏来る」だが、小魚の名を入れるともっとよい |
| 留守頼む夫に買ひおく柏餅 | 久保田けい子 | このこまやかな心遣いこそ夫婦円満の秘訣 |
| 駆け抜けし龍馬の息吹き若葉燃ゆ | 清家幸子 | 嘗て龍馬もこの径をかけ抜けたのであらうか 若葉鮮烈 |
| 万歩計距離のばしつつ青きふむ | 浅川道子 | 日課の散歩であらう 健康のため毎日距離をのばし乍ら新保の山野をたのしんでいる姿がみえる |
| 鉢植えのどくだみが野の風を恋ふ | 宮本ミユキ | どくだみは野草なので鉢に植えても野性は失はない |
| 老鴬の頭上に鳴きて遠くにも | 河野ミツヱ | 鴬は一渓に一番ひと云れます 渓毎に鳴く声がきこえます |
| どうしても仲よくなれぬ蜘蛛と住む | 伝 | この句くりかえしてお読み下さい 意味深長 |