 |
| 山本城全景 |
山本城は、富山県南砺市山本にある平山城です。
築城時期ははっきりしたことは不明ですが、源義家が活躍していた頃と言われていますので、平安時代後期ということになります。当然ながら築城者もはっきりしません。
ただ、源平合戦時点で越中国には福光城にあった石黒太郎光弘が木曽義仲に属しており、寿永二年(1183年)には石黒光弘は倶利伽羅合戦の勝利に際して尽力したといわれています。この石黒党が山本城を築城していたとしても不思議ではないですが・・・。
南北朝内乱期には、やはり石黒党の末裔である石黒左近大夫成行が宮方に属していたことが知られていて、興国三年(1342年)の冬には、南朝の宗良親王が石黒氏の館に赴いています。
戦国期には山本城に石黒太郎光秀の次男宗五郎が拠っていたとされていますが一門の意思に反したため城を追われています。
さらに木舟城にも石黒氏が拠っていましたが、天正二年(1574年)七月に上杉謙信によって攻め落とされています。
さらに『信長公記』によれば、天正九年(1581年)七月に「越中国木舟城主石黒左近、家老石黒与左衛門……一門三十騎ばかり上国。佐和山にて惟五郎左衛門生害の儀申し付けらるべきの処に、長浜まで参り、……石黒左近町屋にこれあるを取り籠め、屋の内にて歴々十七人生害候。惟住者も。能者二、三人討死候」と見え、石黒氏一門は織田信長に滅ぼされています。
その後、越中には織田氏配下の佐々成政が入り、山本城には山本志摩守が入っています。しかし天正13年(1585年)、佐々成政が豊臣秀吉に降りるとこの一帯も前田氏の領地となっていて、山本志摩守も城を退去していると思われます。翌年には佐々成政も越中から肥後に移っていて、越中一国が前田氏の領地もしくは蔵入地となっているので、この城も戦略的価値を失っていて、廃城となっていると考えられます。
元々、この一帯は越中と加賀の国境に近く、この城は位置的には国境警備の拠点として十分に戦略的価値があるはずですが、現在の遺構を見る限りにおいては、単郭の小規模な城で軍事拠点としては心許ない造りです。
実際の規模は現在の西側にもっと郭があったのですが、それを勘定に入れてもまだ小規模で、実際の戦闘に役立つとはちょっと思えません。特に戦国末期になると鉄砲を装備しているのでこのような城は良い餌食になってしまうでしょう。
もっとも戦国期には、もっと大きな城だったのかもしれませんが、
 |
 |
| 山本城へはここから登ります |
説明板ですがかすれていて・・・ |
 |
 |
| 郭の中央には石垣と石碑があります |
説明板ですがかすれていて・・・ |
 |
 |
| 虎口のような地形だが |
石垣は後世のものでしょうが・・・ |
 |
 |
| 削平地はかなり平坦です |
南西側から主郭を望む |
 |
 |
| 西側の切岸ですがここには郭が延びていたようです |
圃場整備でこの部分の郭は削られてしまった |
 |
 |
| 土塁の高さはなかなかです |
北側の切岸 |
 |
 |
| ここが虎口のようなのですが・・・ |
中央から左側に虎口のような地形があります |
 |
 |
| 帯郭がありました |
主郭の外側を帯郭が巡っています |
 |
 |
| 石碑は日露戦争での戦没者を慰霊するものです |
石垣の周りの平坦地 |
 |
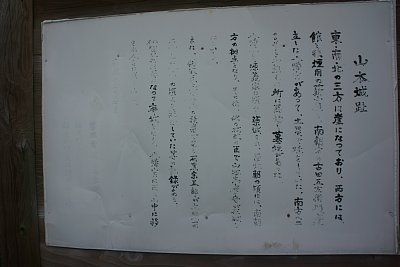 |
| 彼岸花が咲いていました |
説明板はかすれていてよく読めません |
 |
 |
| 全景を見ると土塁の高さは相当のものです |
石碑があるので圃場整備でも城を残したのでしょう |
|
| 住所 |
富山県南砺市山本 |
形式 |
平山城 (比高5m) |
| 遺構 |
曲輪、土塁、虎口 |
築城者 |
不明 |
| 施設 |
案内板 |
城主 |
石黒宗五郎、山本志摩守 |
| 駐車場 |
無料 |
築城年 |
平安時代後期 |
| 文化財 |
なし |
廃城年 |
天正13年(1585年)以降 |
|
|